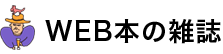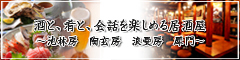〔大森望〕
1月『オーパーツ 死を招く至宝』蒼井碧(宝島社文庫)
2月『アンフォゲッタブル』松宮宏(徳間文庫)
5月『グッド・オーメンズ』 ニール・ゲイマン&テリー・プラチェット/金原瑞
人・石田文子訳(角川文庫)
5月『涼宮ハルヒの驚愕』谷川流(角川文庫)
6月『ビビビ・ビ・バップ』奥泉光(講談社文庫)
7月『三体』劉慈欣/大森望・光吉さくら・ワンチャイ訳(早川書房)※
7月『クサリヘビ殺人事件 蛇のしっぽがつかめない』越尾圭(宝島社文庫)
8月『夏をなくした少年たち』生馬直樹(新潮文庫)
『フロリクス8から来た友人』フィリップ・K・ディック/大森望訳(ハヤカワ文庫SF)※
『おうむの夢と操り人形 年刊日本SF傑作選』大森望・日下三蔵編(創元SF文庫)※
10月『死なないで〈新装版〉』井上剛(徳間文庫)
12月『息吹』テッド・チャン(早川書房)※
〔ひとこと〕
翻訳・編纂などに自分が関わった作品(末尾に※印を付したもの)を除くと、2019年に出た純粋な文庫解説は8本。5本にまで激減した2018年に比べてやや持ち直した感じですが、それ以前の9年間(平均13冊強)と比べるとやっぱり少ない。もっとも、最近だんだん文庫解説を書くのに疲れてきて、昔よりずいぶん時間がかかるようになっているので、まあこのくらいがちょうどいいかも。
ところで、2019年に刊行された北上次郎氏の『書評稼業四十年』(本の雑誌社)には、文庫解説稼業についてもかなり詳しく書かれているので、毎年このリストを見るのを楽しみにしているような人はくれぐれもお見逃しなく。
〔杉江松恋〕
1月『秘密』ケイト・モートン/青木純子訳(創元推理文庫)
3月『ノッキンオン・ロックドドア』青崎有吾(徳間文庫)
4月『Xの悲劇』エラリー・クイーン/中村有希訳(創元推理文庫)
6月『短編ベストコレクション 現代の小説2019』日本文藝家協会編(徳間文庫)
『夫が邪魔』新津きよみ(徳間文庫)
7月『世界を救う100歳老人』ヨナス・ヨナソン/中村久里子訳(西村書店)
『デブを捨てに』平山夢明(文春文庫)
『ザ・ボーダー』ドン・ウィンズロウ/田口俊樹訳(ハーパーBOOKS)
8月『喜劇 愛妻物語』足立紳(幻冬舎文庫)
『悪寒』伊岡瞬(集英社文庫)
『ひとり旅立つ少年よ』ボストン・テラン/田口俊樹訳(文春文庫)
『カジノ・ロワイヤル』イアン・フレミング/白石朗訳(創元推理文庫)
『戦場のコックたち』深緑野分(創元推理文庫)
11月『赤毛のレドメイン家』イーデン・フィルポッツ/武藤崇恵訳(創元推理文庫)
『クローバーナイト』辻村深月(光文社文庫)
『破滅の王』上田早夕里(双葉文庫)
12月『失われた地平線』ジェイムズ・ヒルトン/池央耿訳(河出文庫)
〔ひとこと〕
2018年は14冊でしたが、2019年は17冊と少し増えました。海外と国内の比率は、前年が6/14だったのに対して今年は8/17、海外小説の解説をもっと書きたいと言い続けてきましたので、これもいい方向に進んでいると思います。以前から熱望していた古典作品をいくつも手掛けることができたのは本当に嬉しくて、以前に手掛けた『トレント最後の事件』『矢の家』に続き、『赤毛のレドメイン家』まで解説を書けて幸せです。あとはヒルトン『学校の殺人』を書ければ創元推理文庫の旧おじさんマークでやりたい本はだいたい揃うのです。
国内は、ありがたいことに作家の指名で依頼をいただいたものが多く、気に入った作品について書くことができました。どれも愛着のある解説です。
解説は本の一部として、おまけの付加価値があるものではないといけないと思っています。そのためには、他の人が書いていない発見を盛り込みたいと思っていますし、作者も気づいていないような角度からの読解がそこに入っていればなおいい。また、作品の欠点だと感じるところは、なるべく指摘するようにもしています。どんな作品だって完璧ではないわけで、その欠点も小説の一部として愛でるのがいちばん有意義な読み方なんじゃないのかな。
〔池上冬樹〕
1月『ママがやった』井上荒野(文春文庫)
2月『英雄の条件』本城雅人(新潮文庫)
4月『密告はうたう 警視庁監察ファイル』伊兼源太郎(実業之日本社文庫)
4月『社賊』森村誠一(集英社文庫)
5月『自殺予定日』秋吉理香子(創元推理文庫)
6月『許されようとは思いません』芦沢央(新潮文庫)
7月『真夏の雷管 北海道警・大通警察署』佐々木譲(ハルキ文庫)
8月『ア・ルース・ボーイ』佐伯一麦(小学館 P+D BOOKS)
10月『海の稜線』黒川博行(角川文庫)
12月『闇という名の娘』ラグナル・ヨナソン/吉田薫訳(小学館文庫)
12月『ジャパンタウン』バリー・ランセット/白石朗訳(ホーム社)
〔ひとこと〕
2010年は17冊、11年は19冊、12年は15冊、13年は21冊、14年は15冊、15年は18冊、16年は27冊、17年は13冊、18年は9冊、そして19年は11冊。平均すると16冊になるが、今後は10冊前後に落ち着くのだろう。みなそれぞれ良書で、読む価値があるのだが、個人的好みであげるなら『闇という名の娘』になるだろうか。これは女性刑事を主人公にした警察小説ですが、同時に女性刑事の私小説ですね。それも老年に達しかけている女性刑事の私小説。こういう書き方もあるのか、いや、こんなに日本の私小説的でいいのかという思いも抱きました(詳細は解説参照)。
なお、『ア・ルース・ボーイ』は新潮文庫に続いての文庫化(つまり二次文庫。ちなみに新潮文庫の解説は山田詠美)。三島由紀夫賞を受賞した名作ですが、資料をあたり、当時の選評を入手して書いてみました。選考委員は江藤淳、大江健三郎、中上健次、筒井康隆、宮本輝という豪華メンバーで、各氏がどのように佐伯作品を評したのか、ぜひご覧ください。その後の佐伯文学を見通す意味でも価値はあると思います。
〔北上次郎〕
1月『まさかまさか よろず相談室繁盛記』野口卓(集英社文庫)
2月『悪魔の赤い右手 殺し屋を殺せ2』クリス・ホルム/田口俊樹訳(ハヤカワ文庫)
『疾れ、新蔵』志水辰夫(徳間文庫)
3月『誰がために鐘を鳴らす』山本幸久(角川文庫)
5月『神奈備』馳星周(集英社文庫)
『猟犬の國』芝村裕吏(角川文庫)
6月『ブラック&ホワイト』カリン・スローター/鈴木美朋訳(ハーパーBOOKS)
『椎名誠〔北政府〕コレクション』椎名誠/北上次郎編(集英社文庫)※
9月『ひりつく夜の音』小野寺史宜(新潮文庫)
10月『愛しい人にさよならを言う』石井睦美(中公文庫)
『影絵の騎士』大沢在昌(角川文庫)
『生者と死者に告ぐ』ネレ・ノイハウス/酒寄進一訳(創元推理文庫)
11月『北海タイムス物語』増田俊也(新潮文庫)
〔ひとこと〕
2019年は、これ以外に「色川武大・阿佐田哲也電子全集」(小学館)の解説を3巻書いたが、純粋な文庫解説は12点(※は編者解説なので)。点数的には例年通りか。いちばん嬉しかったのは、『椎名誠〔北政府〕コレクション』。以前から椎名誠の「北政府もの」をまとめてみたかったので、長年の夢が実現して嬉しかった。2020年は、「色川武大・阿佐田哲也電子全集」の解説を7巻書かなければならないので、文庫解説の点数は減るかも。しかし出来れば、2019年同様の12点はクリアしたい。怠けないように、とただいま自分に言い聞かせている。